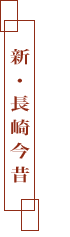 |
|
第十九回/長崎の町の発展(七)開港後に開かれた町 榎津町、本古川町、東古川町、西古川町 |
|
|
榎津町は、江戸時代の初めに造成された外町の一つで、筑後榎津、現在の福岡県大川市の家具商が多く居住したことから榎津町と命名された。しかし、昭和41(1966)年の町界町名の変更により万屋町と鍛冶屋町に分割され、榎津町の町名はなくなった。
幕末期、榎津町、現在の万屋町5番の地にあった料亭清風亭(せいふうてい・亭主吉岡兵助)は、幕末動乱期の大舞台の一つであった。
というのは、この清風亭で慶応3(1867)年1月13日、坂本龍馬と土佐藩参政(重役)後藤象二郎の会談が行われ、その結果、4月に龍馬を隊長とする海援隊が組織されたことから、以後、龍馬らは大政奉還に向ってまい進して行くのである。また、この会談によって土佐商会が開設された。 |

▲坂本龍馬像(風頭公園) |
|
|
|
ところで同料亭の場所は、ずっと榎津町とあるだけで、その正確な場所は不明であったが、大光寺(鍛冶屋町)の過去帳や明治初期の榎津町の地図などから榎津町65番地、現在の万屋町5番10号一帯と確定された。
古川町も江戸時代の初めに造成された外町の一つで、大村藩領戸町村大浦郷、現在の長崎市古河(ふるこ)町一帯の人たちによって造成されたことから古川町と命名された。以後、現在の東古川町の地に歌舞伎町や新歌舞伎町、川添町が造成されたように、各地から人々が移住、町域を拡大していった。
寛文12(1672)年、幕府は、長崎の63か町を面積や人口を均等にするため大きな町を2か町に分割したが、古川町はもっと大きい町ということで、本古川町、東古川町、西古川町の3か町に分割された。
これら古川町の内、本古川町は本(もと)からあった古川町ということ、東古川町は、最初、現在の中通りを挟んで北側が歌舞伎町、南側が新歌舞伎町と呼ばれたが、後に古川町になり、さらに古川町の東の方ということで東古川町、西古川町は、東古川町の天満宮の鳥居に「川添町」と刻まれているように、最初は川添町と呼ばれたが、後に古川町になり、さらに古川町の西の方ということで西古川町になったと考えられる。 |
|
|
|

▲東古川町天満宮
|
ちなみに昭和41年の町界町名の変更で、本古川町は、古川町、万屋町に、西古川町は、諏訪町、古川町、万屋町にそれぞれ分割され、本古川町と西古川町の町名はなくなった。東古川町も同年の町界町名の変更で、古川町になり、東古川町の町名はなくなったが、平成19(2007)年に復活、再び東古川町となった。
|
|
|
|
本古川町47番地、現在の万屋町6番には杉本わかが開業した料亭菊本(きくもと)があった。わかは、照菊という名の売っ子芸者で、大正11(1922)年、長崎を訪れた芥川龍之介もぞっこん惚れ込み、大作河童図屏風を描き与えている。
この屏風は、菊本の名物となり、長崎を訪れた著名人は、決まってこの屏風を鑑賞、その感想を「河童供養帖」に認めている。わかは、昭和52(1977)年に84歳で死去。屏風は、長崎歴史文化博物館に収蔵されている。 |

▲杉本わか |
|
|
|

▲西古川町傘鉾の飾 |
西古川町は、大相撲にゆかりの町であった。というのは、大相撲の初代横綱明石志賀之助は長崎に生まれたとか、晩年には長崎で暮らしていたとかいわれているからである。その弟子浮船百度兵衛も長崎の、それも西古川町の住人であったとかで、江戸時代、西古川町は、長崎における大相撲の興行を全て取り仕切るなど、大相撲とは切っても切れない関係を持つようになった。そのようなことから西古川町の傘鉾の飾(だし)は、現在でも弓に日月の軍配と相撲故実を記した巻物で、奉納踊も相撲にちなむものである。 |
|
|
|
|
|
|
NPO法人長崎史談会会長 原田博二 |
|
|
|
長崎今昔トップに戻る >> |